


既存事業が安定成長を続けるなかで、次なる柱となる新規事業を生み出すのは、決して簡単なことではありません。いわゆる「イノベーションのジレンマ」とも呼ばれるこの現象に、多くの企業が直面し、課題を抱えているといわれています。
ビジネスSNSとして2012年に産声を上げた「Wantedly」。サービス開始からわずか5年で東証マザーズに上場するなど、HR業界の中でも注目を集めるスタートアップです。
上場後も安定した成長を続ける同社は、2021年から新たに「Engagement Suite」と冠し、福利厚生サービス「Perk(パーク)」、モチベーション・マネジメントツール「Pulse(パルス)」、社内報プラットフォーム「Story(ストーリー)」という3つのプロダクトをリリース。採用領域にとどまらず、従業員エンゲージメントという新たな領域にも踏み出し、積極的に新規事業開発に取り組んでいます。
今回の「月刊タレンタル」では、そんなEngagement Suite領域を率いる橋屋 優理(はしや ゆたか)さんに取材。サービスリリース直後の2022年にウォンテッドリーへ参画し、以来、事業成長を牽引してきた橋屋さんに、“第2の柱”となる事業を生み出すうえで欠かせない視点について、お話をうかがいました。

2009年4月、早稲田大学を卒業した橋屋さんは、シャープ株式会社に新卒で入社し、法人営業や営業企画といった業務に従事しました。
私がシャープに入社したのは、リーマンショック直後の2009年というタイミングでした。世界不況の影響を受け、シャープに限らず、多くの企業が大きなダメージを受けていた時期です。もともと私はHR領域に関心があり、人事部門への配属を希望していましたが、そうした背景もあって、最初の配属は法人営業になりました。
当時の私は、それほど意識が高い就活生ではなかったので、「きっとこのままシャープで働き続けるんだろうな」と思っていたんです。でも、リーマンショックという出来事を経験したことで、私の価値観は大きく揺さぶられました。
シャープのような大企業であっても、会社が一生守ってくれる時代ではない――。これからは、自分でキャリアを切り開いていかなくてはいけない、という想いが強く芽生えました。

約4年間シャープで働いた橋屋さんは、もともと関心のあったHR領域でのキャリアを自ら切り拓くべく、エムスリーキャリアへと転職します。
やっぱり、HR業界への関心をどうしても捨てきれず、転職を決意しました。
エムスリーキャリアに惹かれたのは、医療という専門領域に特化した人材ビジネスという独自性に加え、非常に優秀な社員が多く在籍していた点です。KPIをはじめとする数値に基づき、逆算して事業を組み立てていくスタイルを学べる点にも強く惹かれましたね。
私は医師領域の人材紹介事業を担当することになり、転職希望者のキャリアカウンセリングを行うCA(キャリアアドバイザー)と、求人企業を支援するRA(リクルーティングアドバイザー)の両方を、ひとりのコンサルタントが一貫して担う両面型のスタイルを経験しました。これは私にとって、大きな学びとなりました。
同時に、人材紹介という手段だけでは解決できない課題があることも実感しました。たとえば、マッチングがうまくいって転職が決まっても、入社後しばらくして辞めてしまうケースがある。入社後のプロセスにもっと関与できれば、人と企業の選択をより正解に近づけることができるのではないか――。こうした思いから、組織開発や従業員エンゲージメントという領域に興味を持つようになりました。
また、エムスリーキャリアでは、タスクフォース的に新規事業開発プロジェクトが立ち上がることが多く、私自身もいくつかのプロジェクトに参加しました。そうした経験を通じて、次第に新規事業開発という領域にも強く惹かれていったんです。
その後、別のスタートアップ2社で新規事業の立ち上げを担当しました。いずれもHR領域でのチャレンジで、そのうちのひとつが、従業員のエンゲージメントを可視化するためのパルスサーベイ事業でした。
ただ、従業員エンゲージメントや組織開発といった領域には、単体でスケールさせることの難しさも感じていました。たとえば採用であれば、「どのポジションを何人採用できたか」といった明確な成果指標があり、費用対効果も示しやすい。一方で、エンゲージメント施策単体では、サービスのROI(投資対効果)を明快に説明するのが難しい側面があります。
だからこそ、採用領域のサービスをすでに持っている企業が、従業員エンゲージメント領域にもサービスを広げていくほうが、事業としての広がりや可能性があるのではないか。そんな仮説を持つようになったんです。
そして、まさにそのような形で、従業員エンゲージメントや組織開発の領域に参入していたのが、当時のウォンテッドリーでした。

こうして2022年にウォンテッドリーへ入社した橋屋さんに託されたミッションは、1年前にリリースされた3つのプロダクト――福利厚生サービス「Perk(パーク)」、モチベーション・マネジメントツール「Pulse(パルス)」、社内報プラットフォーム「Story(ストーリー)」を成長させることでした。
これらのプロダクトは、もともと既存事業である「Wantedly」の顧客満足度向上や継続率改善を目的とした付帯サービスとしてスタートしたものです。しかし、単なる補完的なサービスにとどめず、将来的には独立した事業としてスケールさせていく可能性について、社内でも議論が始まりつつあるタイミングでした。
私が参画した当時も、これらのサービスにはすでに売上や利益といった数値目標が設定されていました。ただ、あくまで「Wantedly」の付帯サービスという位置づけが強く、目標の根拠や、そこにつながるビジョンが明確に描かれていたとは言えない状況でした。
当時のプロダクトは、まだ同業他社のサービスと比べて見劣りする部分も多く、機能やサービスの拡充に取り組みながら、まずは足元の売上を確保していくことで手一杯でしたね。
そして入社から1年が経った頃、私は正式に事業責任者となり、ひとつの目標を掲げました。それが、「2030年までに、現在の15倍規模の売上を達成し、このプロダクト群をウォンテッドリーにおける“第2の柱”に育てる」という、いわば“ムーンショット”的な目標です。
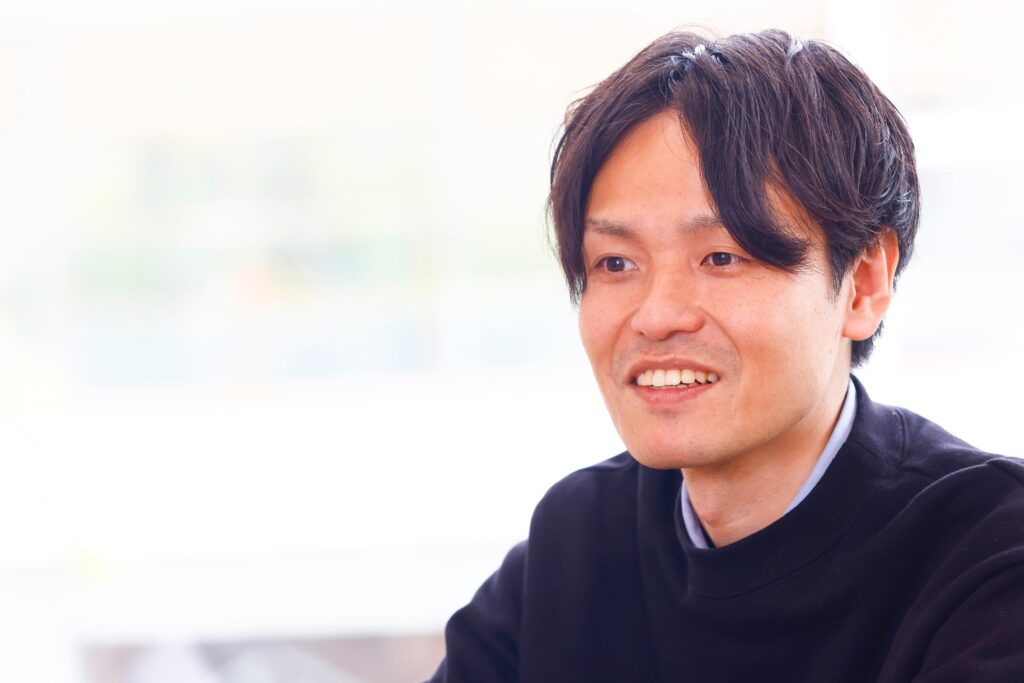
“ムーンショット”とは、月へのロケット打ち上げのように、実現の難易度は非常に高いものの、成功すれば圧倒的な成果を生み出す可能性のある、大きな挑戦や計画を指す言葉です。
一定規模の既存事業を持つ企業における新規事業開発では、求められる成長スピードや売上規模の目標も大きく、場合によっては、単一事業での起業以上に難しい側面を持ちます。上場企業であるウォンテッドリーにおいて、“第2の柱”としての期待を背負う新規事業には、社内はもちろん、投資家や市場からも大きな注目が集まっています。
こうした環境の中で、その重責を担う新規事業開発チームに、どうすれば一体感をもたらし、同じ方向を向いてもらえるのか。橋屋さんは、このテーマにどのように向き合い、取り組んでいったのでしょうか。
2030年に、現状の15倍という売上を目指す目標は、もちろん壮大で、決してラクな計画ではありません。ただ、当社が狙っている市場の規模や、現在の数値の積み上げから逆算していくと、実現可能性のある月次・年次の数値計画に落とし込めています。目標としても適切な水準だと考えていますし、それはチームメンバーも同じ見解です。
とはいえ、それ以上に大切なのは、「なぜウォンテッドリーが、すでに先行プレイヤーが多数存在する従業員エンゲージメント市場に挑戦するのか」という問いに、きちんと答えられることです。
この挑戦の先に、当社が掲げる“究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす”という理念がどうつながるのか――。この「ビジョンとの接続」こそが、もっとも重要だと感じています。
そのためにも、私自身がまず言語化できるように、「そもそも福利厚生とは何か?」という基本から改めて学び直しました。
たとえば、サイバーエージェントの女性活躍推進制度「macalonパッケージ」や、NOT A HOTELの旅行補助制度のように、福利厚生は企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を推進する重要な手段であるべきです。
ウォンテッドリーが目指す“究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす”というビジョンを実現していくうえでも、この領域での事業展開は不可欠だという確信を、私自身が持てるようになりましたし、それをチームメンバーも納得できるかたちで共有することが、なにより重要だと思っています。
さらに、チーム内だけでなく、社内の他部署に対する発信や共有も欠かせません。たとえ現時点で売上規模が既存事業に及ばなくても、事業や施策の進捗を、私だけでなくチームメンバー自身の言葉で積極的に発信する機会を意識的に設けています。
その積み重ねによって、社内でも存在感を高め、「このチームは面白いことをやっている」と一目置かれるようになることが、新規事業として非常に大切な取り組みだと感じています。

最後に、橋屋さんご自身がウォンテッドリーという環境でこの福利厚生というマーケットに挑戦する理由についてもうかがいました。
福利厚生というマーケットでは、プロダクトを「T字型」に拡張していくことが必要だと考えています。
横の軸は、従業員が受けられるサービスのラインナップを広げていくこと。縦の軸は、それぞれのサービスに対して、当社ならではの独自性を打ち出していくことです。
一般的な新規事業では、まず縦軸、つまりニッチな分野で独自性を出していくアプローチが優先されることが多いですが、このマーケットにおいては横軸の拡張を先行させる必要があると考えています。そしてこの横軸の拡張とは、すでに存在する類似サービスを模倣し、まずは劣後しない状態をつくる作業でもあり、非常に時間がかかります。
加えて、先ほどもお話ししたように、従業員エンゲージメントの領域は費用対効果の可視化が難しく、売上や利益といった明確な指標が立ち上がるまでにも時間を要するんです。
つまり、時間をかけて横に広げる努力と、成果が見えにくいという特性の両方を抱えた分野だからこそ、私ひとりで起業しても実現は難しい。こうしたチャレンジは、上場企業であるウォンテッドリーという環境だからこそ取り組めるものだと感じています。
今ある環境を最大限に活かして、掲げた目標をなんとしても実現していきたいですね。
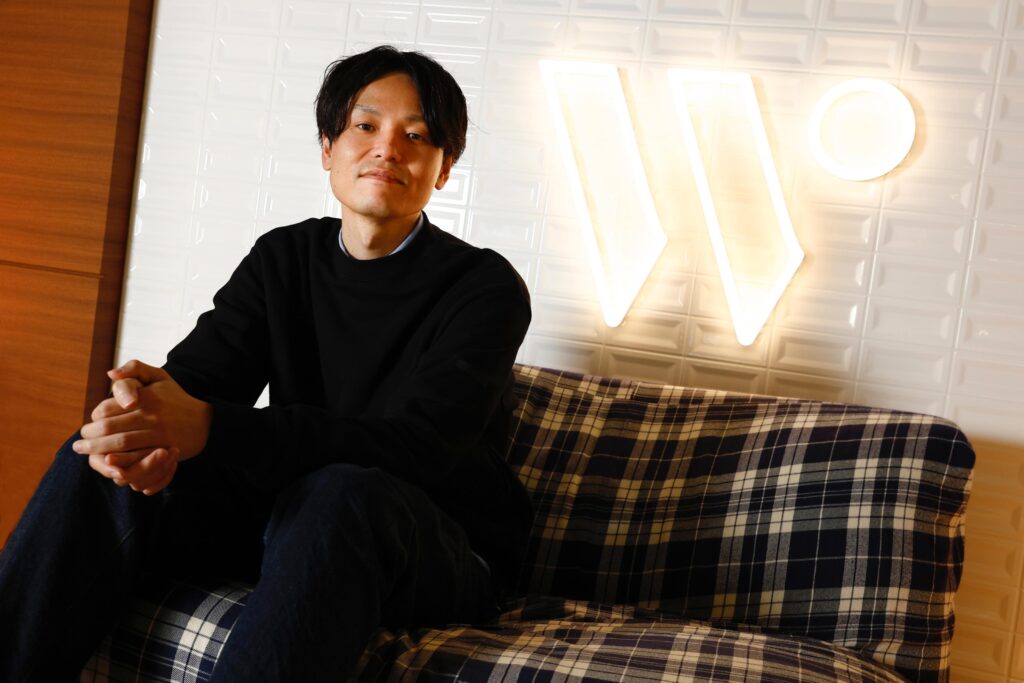
橋屋 優理(はしや ゆたか)
ウォンテッドリー株式会社 Engagement事業部 事業部長
2009年4月、シャープ株式会社に新卒入社。法人営業や営業企画を経験したのち、エムスリーキャリアへ転職し、医師領域の人材紹介事業に従事。HR系スタートアップ2社では新規事業の立ち上げを経験し、2022年にウォンテッドリー株式会社に参画。現在は、同社が展開する福利厚生サービス「Perk(パーク)」、モチベーション・マネジメントツール「Pulse(パルス)」、社内報プラットフォーム「Story(ストーリー)」の3つのプロダクトを管掌する、Engagement Suite事業の責任者を務めている。
取材・執筆:武田 直人 / 撮影:山中 基嘉
副業をお考えのみなさんへ
ご覧いただいている『月刊タレンタル』を運営するtalental(タレンタル)株式会社では、BizDev領域の即戦力人材レンタルサービス「talental」を提供しています。
現在、副業・フリーランス人材のみなさんのご登録(タレント登録)を受け付けています。タレント登録(無料)はこちらから。
これまで培ったスキルやノウハウを活かして、さまざまな企業のプロジェクトに参画してみませんか?