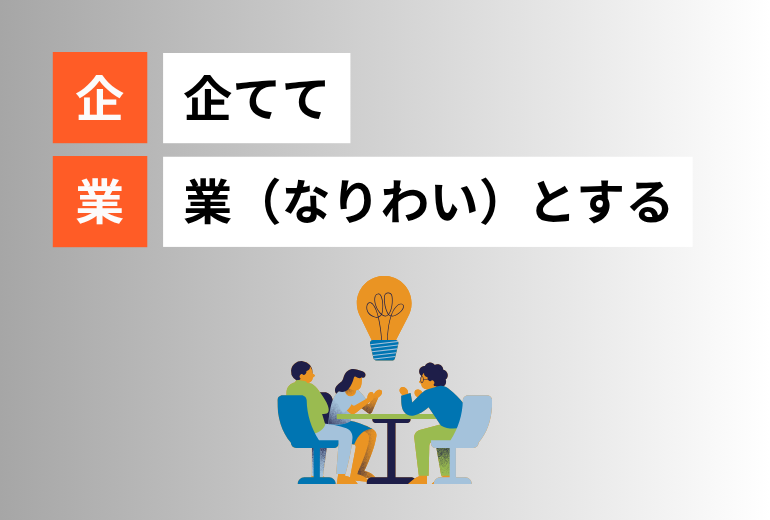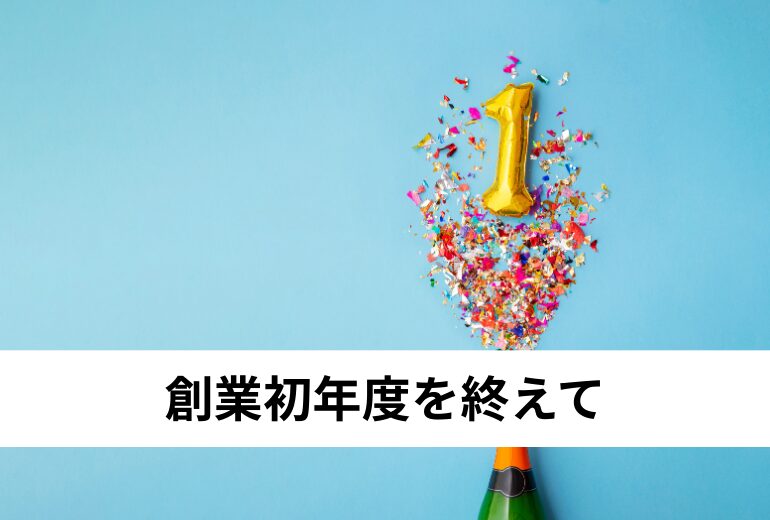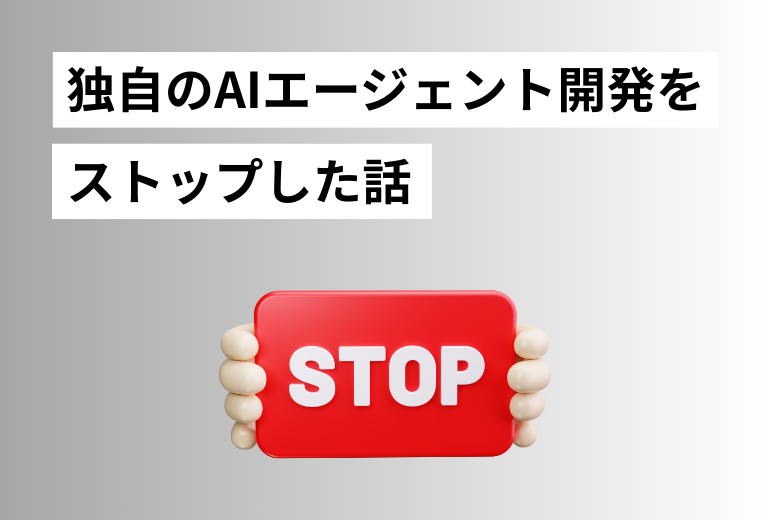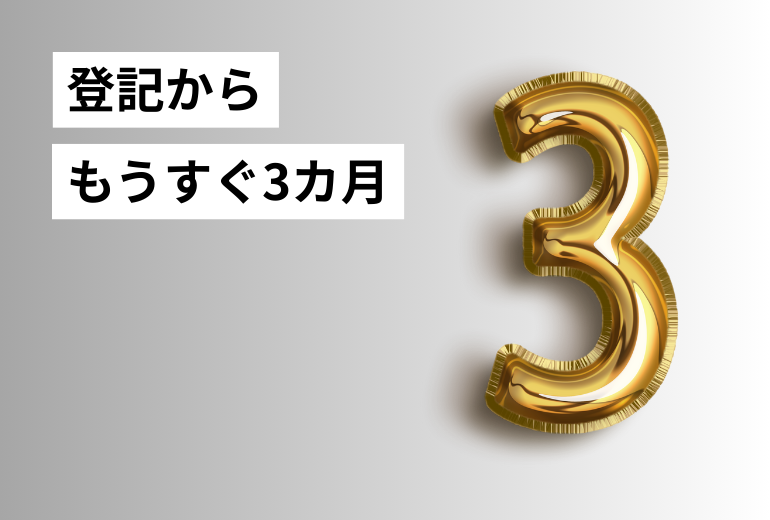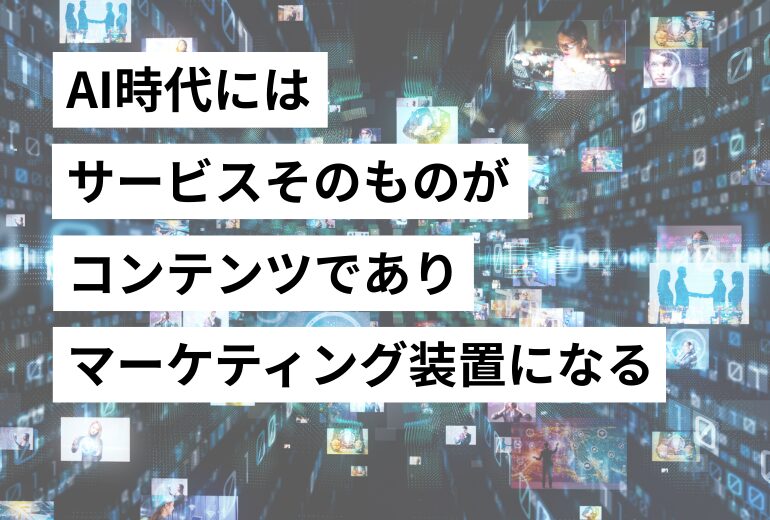先週金曜日は、当社クライアントの20期のキックオフでした。そこで取締役の方が語っていた、「企業とは企てて業(なりわい)とすること」というメッセージが印象に残っていたので、家に帰ってから色々調べてみました。
「企業」ということばは、明治時代に日本に入ってきたさまざまな西洋語を翻訳するときに生まれたもので、特に誰が翻訳したかは明らかにはなっていないのですが、「enterprise」という英語を翻訳してできたようです。というわけで、元のenterpriseということばの起源も見てみましょう。
大元はラテン語で「prehendere(つかむ、握る)」という単語があり、それが古フランス語で「entreprendre(試みる、引き受ける)」という単語に変化していきました。そこから中英語で「enterprisen(挑戦する、引き受ける)」という言葉になり、近代英語で「enterprise(冒険的な試み、事業)」となっていきます。つまり、「enterprise」とは、“リスクを承知したうえで、何かをつかんで始めること”を意味する単語であるということです。
これが日本語翻訳されたのが「企業」ということば。元となる「enterprise」の語源と合わせて考えると、“リスクを認識しながらも、何かを企てて、それを業(なりわい)にしていくこと”という意味を持つことがわかります。
BizDev(事業開発)の仕事ってまさにこういうことだよなあと、改めて感じました。自分自身も常に企てて、新たな業(なりわい)を生み出していけるようにありたいと思ったので、備忘録としてブログにまとめておきました。