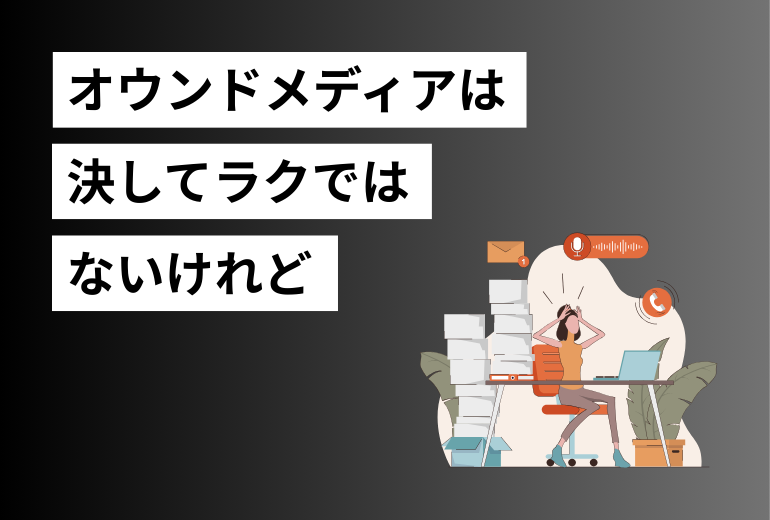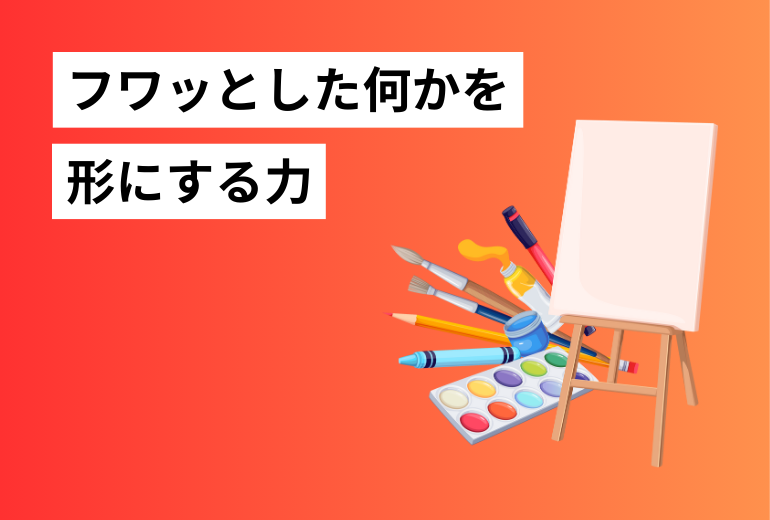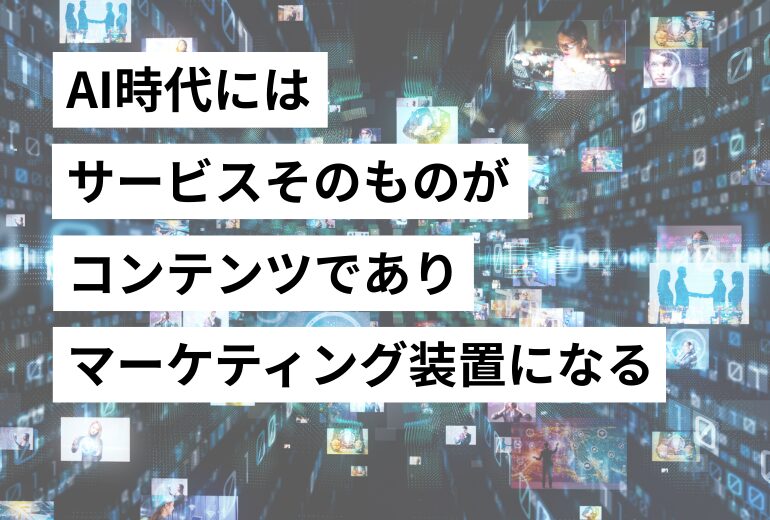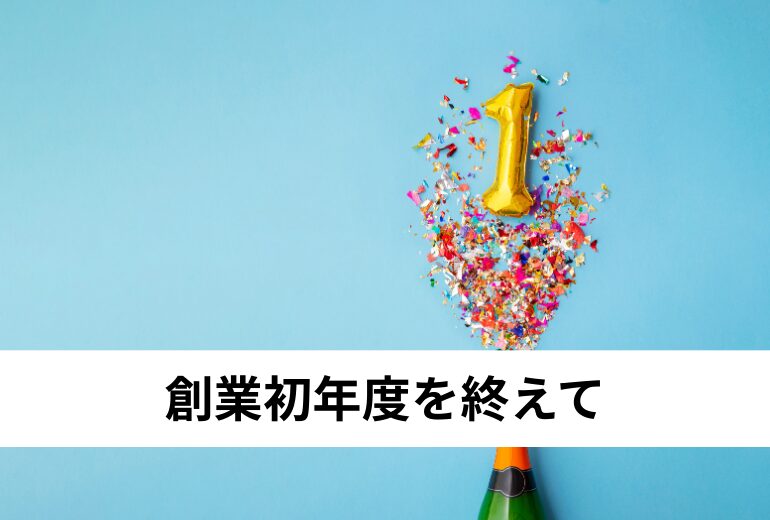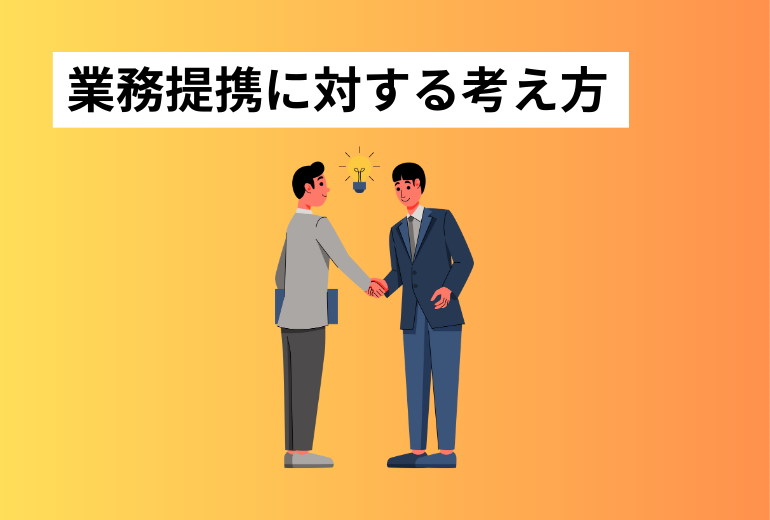まずはじめに、数日前にちょっと話題になっていたこのブログをご一読ください。
ここに出てくるような「AIで作れば安くできるんですよね?」というシーン、自分はWeb制作をメインとした事業をやっているわけではないので、まだ直接言われたことはないのですが、けっこうあちこちで出てきてそうな話です。
このような、AIによる仕事の価値の変化が実際にどんな風に発生するのか考えてみましょう。
いったん適当な金額で設定しますが、従来のWeb制作はこんな感じです。制作を内製で行う場合は販管費だったり、外注する場合は原価だったりするかと思いますが、いったん細かい費目は無視してこれら制作にかかるコスト一式を「制作費」としてまとめています。
<Case1>
- 売上:100万円
- 制作費:60万円
- 利益:40万円
当然クライアントは100万円を支払うわけですが、どんな価値を買っているのかというと、作業としての制作費に加え、その制作会社のマーケティングに関する知見やブランディングのノウハウなど、これまでその会社が培ってきた価値への対価が乗っかっています(制作会社側からすれば営業人件費やファシリティコストが乗っかっているともいえますが、いったんはクライアント視点で整理します)。
「AIで作れば安くできるんですよね?」というのは、ここでいう制作費が生成AIを使うことによって下がってますよね?ということを一義的には意味していると思うのですが、生成AIを活用する制作会社にも学習コストが発生しているはずで、本来であれば価格に反映する必要はありません。
この場合、
<Case2>
- 売上:100万円
- 制作費:20万円(仮に3分の1として)
- 利益:80万円
となるはずです。いまの生成AIの登場による受託ビジネスの盛り上がりは、こうした形で生成AIをしっかり活用できる会社がその恩恵として利益を大きく確保できるということを意味します。
ただ、すでにそうなっているとも言えますが、市場が盛り上がるほどレッドオーシャン化するのが速いということでもありますから、このCase2の価格では徐々に販売が厳しくなり、競争激化のなかで下がる部分が出てくるでしょう。また、並行してクライアント側も生成AIのスキルを身に付け、要件定義など従来受注者側が担っていた業務を侵食するということも影響するかもしれません。
そうした場合、
<Case3>
- 売上:60万円
- 制作費:20万円
- 利益:40万円
ということが起きてきます。とはいえ、上記のような売価が維持できている限りにおいては、Case1と同じ利益確保が可能です。
ただ、実はここで大きな変化があることを認識する必要があります。
Case1においては、売上に占める制作費は60%ですから、クライアントに提供する価値の半分以上は「作る」という行為そのものです。一方、Case3の場合、利益の額は変わりませんが、クライアントに提供する価値の7割近くは、受注者の持つ知見やノウハウということになります。
もはやこの提供価値は、制作会社ではなくコンサルティング会社のそれといって差し支えないでしょう。すなわち、クライアントは「作ってもらう」という行為に対価を払うのではなく、知見やノウハウに対価を払うという考え方に変わります。
この提供価値に占めるウェイトの変化を、受注者側は正しく認識しないといけないなと思っています。制作会社から見れば確保できる利益はたとえ変わらなくとも、発注者たるクライアントの「何にお金を払うのか」という本質部分は大きく変化しています。
今回はWeb制作を例にして考えていますが、それ以外の領域でも似たような事象が起きてくるでしょう。価値の本質を意識しながらサービス設計していくことが、より一層求められてくるように思います。