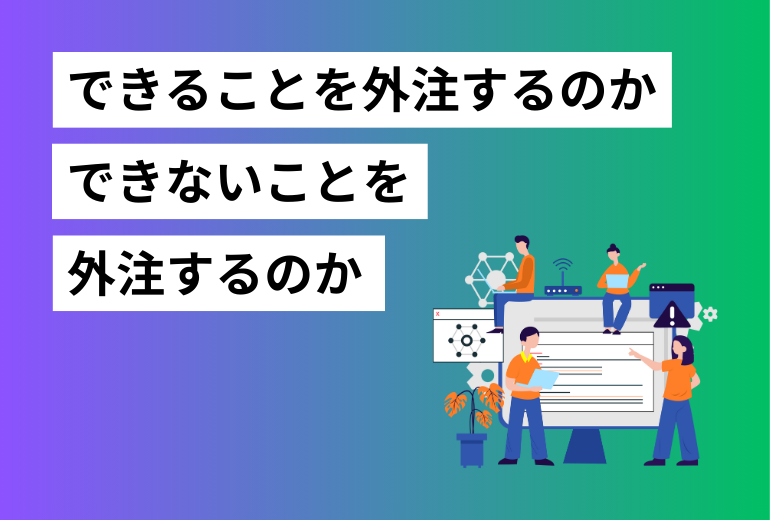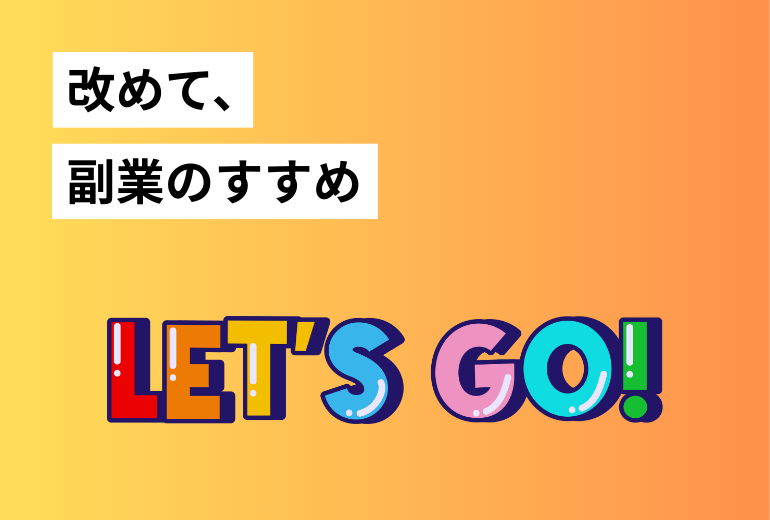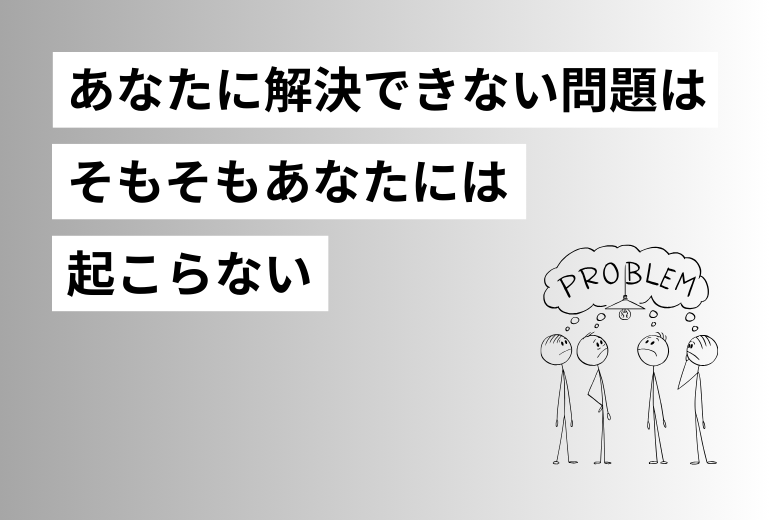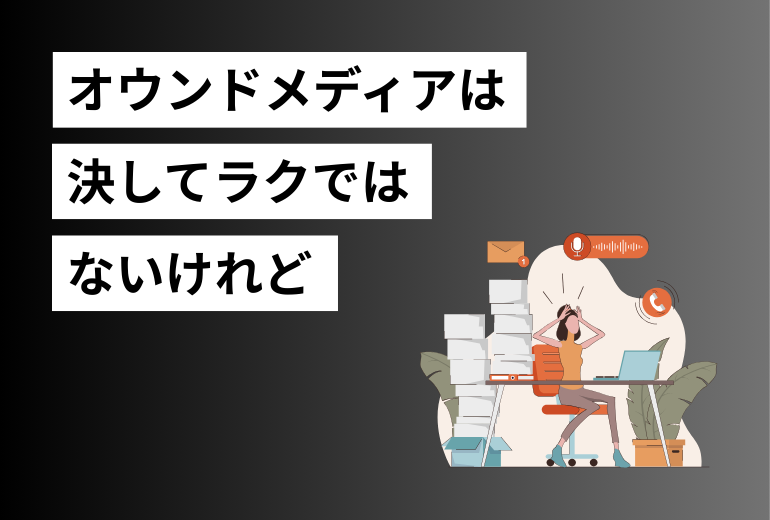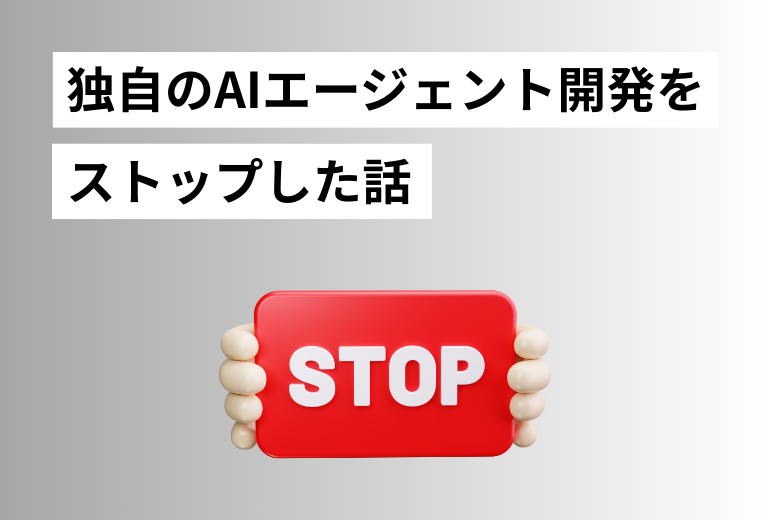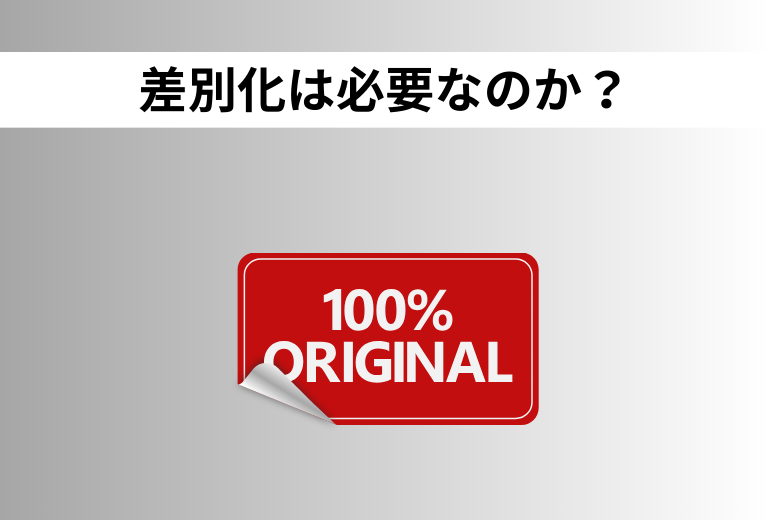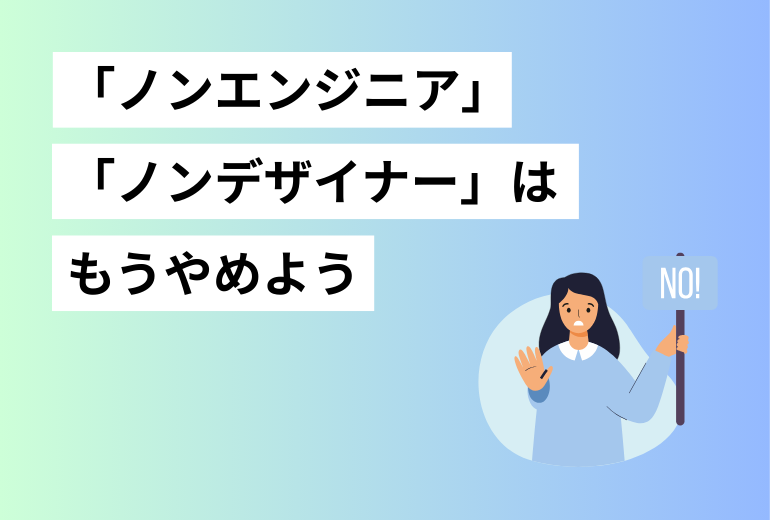労働人口減少という大きな社会問題に直面する日本。企業の採用難易度が高くなるなか、各社はコア機能に人材を集中し、それ以外はアウトソースする流れがより顕著になっていくと思われます。また、クラウド環境やSNS、そしてAIといったさまざまな技術の進化によって、業務の受け手となる個人が独立しやすくなるというのも、その変化を加速させるように思います。
そうしたなかで重要になってくるのが、「外注」するスキルやノウハウ。もはや外注することは企業の存続において不可欠な要素となり、すべてを内製化するのは難しいというか、きわめて非効率になります。
より自社に合う委託先を見つける力、そのパフォーマンスを引き出す力が求められるようになり、それができないと委託先からも見限られてしまうことになりかねません。採用力と同じように、外部の優秀な人材や委託先を調達し最適化する「外注力」とも呼べる力が大事になってくるでしょう。
ここでひとつ考えたいのが、表題にもある、できることを外注するのか、できないことを外注するのか、という点です。
もちろん業務の種類によって正解が変わる可能性はありますが、個人的には、「できることを外注すべき」と考えています。もしくは「ある程度できるようになってから外注すべき」と言ってもいいかもしれません。
外注と聞いて想起しやすい分野としては、法務・経理などのバックオフィス業務、システム開発、Webサイトや各種印刷物などがあります。あとは営業や採用なども代行がさかんになってきました。
「できないことを外注する」というのもひとつの選択肢としてはあろうかと思います。しかし、発注者がまったく知見を持っていないと、コストの最適化が実現できない、その業務の品質やスピードの管理ができない、という状況に陥ってしまう可能性が高くなります。
今の時代、やり方を調べる方法はいくらでもあります。
たとえばAIエージェントの開発のように一見難易度の高そうなプロジェクトであっても、いきなり委託先探しをはじめるのではなく、まずは自分でChatGPTにやり方を相談してみて、どのようなツールやサービスを使えば実現できるのか、どんなリスクがあるのかをしっかり洗い出しておく。いったんGASなどブラウザベースのローコードツールとChatGPTのAPIを連携させれば、AIエージェント的なものを自作してみることはできますから、それをもとに実用におけるボトルネックはなんなのか、どこに課題が出るのかを明確にしたうえで、そこをクリアできそうな委託先を探す。
LPやサイト、動画、印刷物の制作であっても、Canvaなどのツールを使って自作してみて、どうしても自分で解決できない品質の壁を明確にしてから委託先を探す。
法務や経理であっても同じです。ChatGPTやGeminiでひととおり壁打ちして懸念点を明確にしてから、その道の専門家に意見を求める。
営業代行や採用代行も同じです。仮にテレアポであっても、まずは自分で架電してみて、どんな時間帯がコネクトしやすいのか、どんなリストが効果的なのかを確認してから、そこをさらに深堀する観点で委託先を検討する。
こうしたまずは自分で手を動かしてみる、調べてみるといった工程を経験するからこそ、外注すべき範囲とそうでない範囲の線引きも明確になりますし、無用なコスト、無用な作業をなくすことができるようになります。
日々の仕事に忙殺されるなかで、これらの時間を確保するのは難易度が高いのも自分自身も感じていますが、こうしたプロセスを通してその分野への知見も深まりますし、何より新たな学びを得ることは、自分自身を豊かにしてくれるというか、シンプルに楽しい。
自分も100%できているわけではありませんが、自社の経営効率最大化のためにも、そして自分個人のためにも、この考え方は大事にしたいと思います。