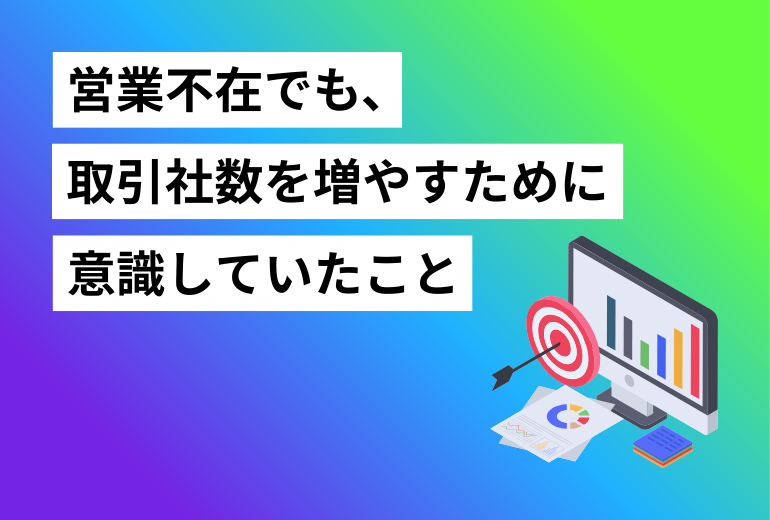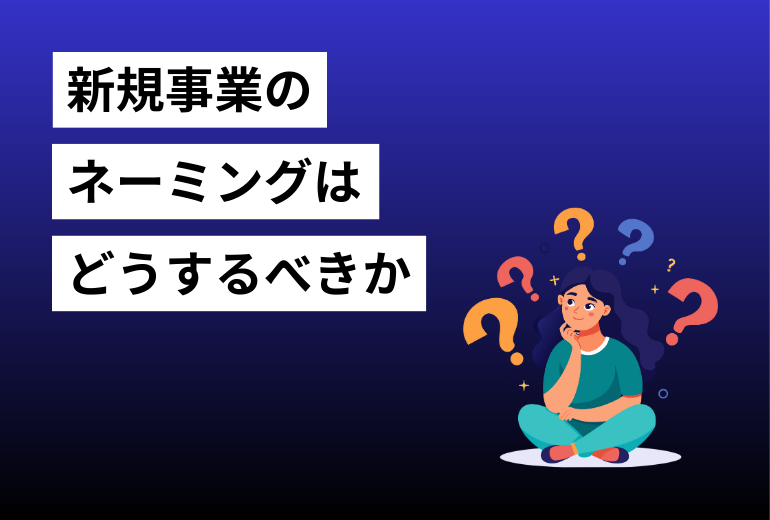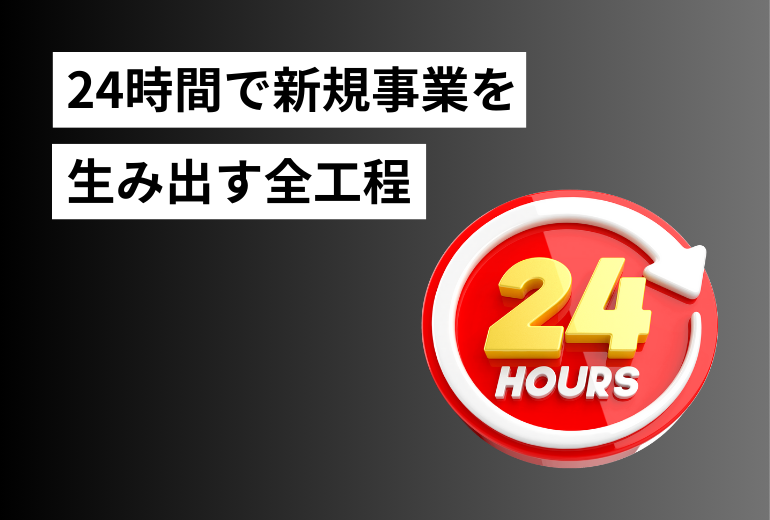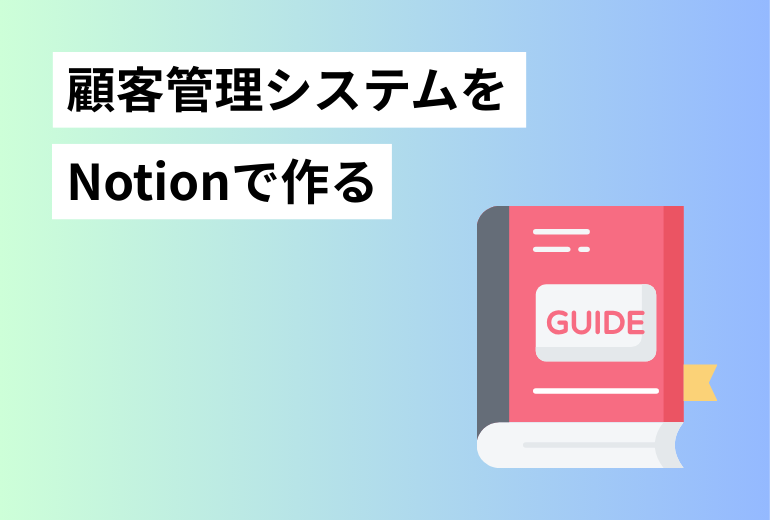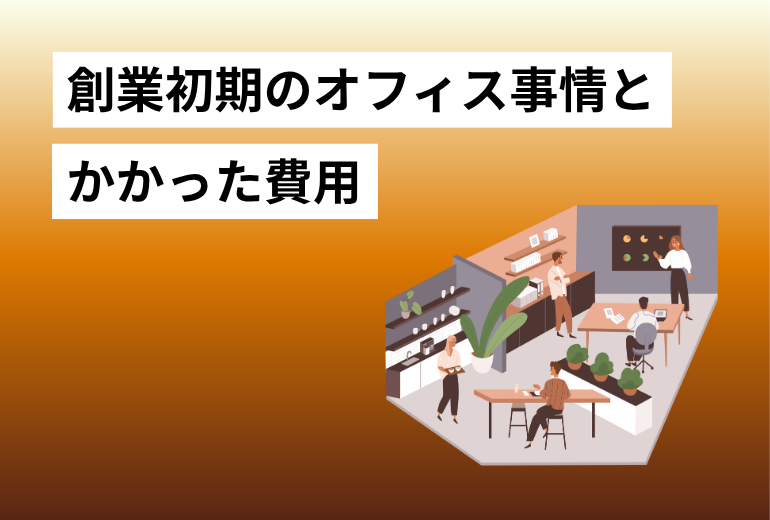talentalでは現在20社強のクライアントに対してサービス提供をしています。現時点では正社員はゼロで、代表である私と、業務委託のメンバーが数名といった感じの組織になっています。いわゆる営業専任の正社員はまだいません。
加えて、設立当初の売上を確実にするために、自分自身もタレントのひとりとして稼働するという選択をしたこともあり、正直自分もほとんど営業活動を行える状態にはありません。でも、事業としての拡大を考えると取引先は増やさないといけない。
この矛盾が生じることは事業開始する前からわかっていましたから、それを踏まえて営業戦略を立てる必要がありました。20社強という数がまったく多いとは思いませんが、いちおう期初計画を超えるレベルの成長曲線は実現できたかなと思うので、今回はそんな話をまとめておきたいと思います。
ひとりコンサルとして活動している方や少人数で受託開発をやっている方など、個人事業主的な売上構成からどう脱却するかという悩みを抱えている方には、もしかしたら参考になるかも…。
ターゲットは、「属性」だけでなく「関係性」を絞る
talentalのサービスは、業種や地域はあまり問いませんが、中小企業・スタートアップ向けのものです。従業員規模は100名未満のお客様がほとんどです。新規事業開発や事業推進を担う、事業開発や経営企画、社長室のような組織を持たない企業に対して、外部人材がその機能を担うといったイメージです。商談相手はほぼ経営者や取締役といった方々になります。
これが顧客属性という観点でのターゲットになりますが、正直これだとまだ広すぎます。さらに絞る必要がありますが、あまりにも属性を絞りすぎてしまうことは、サービスの拡張性に対するキャップを決めてしまう可能性もあるので、私としてはこれ以上絞るのは避けたかったのが実情です。
そのため、属性を絞るのではなく「関係性を絞る」ということを選択しました。代表である私自身がFacebookで直接つながっている知人のうち経営者や取締役ポジションにいる方々を介して、その知人ぐらいまで。すなわち「2次のつながり」までが当社にとってのターゲットであるという風に設定しました。
むやみにアウトバウンドを行うのではなく、FacebookやXでの日々の発信をベースに、知人のみなさんに当社のことを思い出していただき、そこから直接問い合わせをいただくか、あるいはその先の知人の方々に紹介していただくような導線設計になります。細かいところでいうと、そういう紹介経由の場合は間違いなく私のプロフィールも見られるため、サービス紹介動画を固定ポストに置いておくようにしています。
このようなターゲット設定をしたうえで、そこからの導線をスムーズにできるようなサービス設計が重要になると考えました。
受注前の企画や提案を不要にする
新規事業開発プロジェクトを受託するための営業活動は、受注前の提案が非常に重たくなることが想像されました。その企業のIRなどの公開情報から事業内容を分析し、課題設定や実際の支援内容を組み立てるなど、膨大な提案書が必要になることが予想されます。
私ひとりで営業活動を完結させることを考えると、こうした提案書作成に時間を要してしまうことはどうしても避ける必要がありますし、仮に失注すればその提案がすべて無駄になってしまいます。
これを避けるために、「新規事業開発プロジェクトを提案する」のではなく、「新規事業開発プロジェクトを支援できる人材を提案する」という形に軸をずらしたのが、talentalのサービスです。こうすることで、プロジェクト自体の提案書は不要となり、どういう候補者がいるかを説明することに重心が移ります。当社では候補者となる人材データの抽出はAIを活用することでかなり自動化しているため、ここで私自身の工数はほぼ発生しません。
結果として、会社設立してから約1年、受注前の提案書作成は一度もやったことがありません。汎用的な会社案内資料ですべての商談が完結しています。
サービス内容をすべて公開する
もうひとつ意識していたのは、先述した導線を考慮し、サービス内容をきわめてシンプルにし、それをオープンな情報として公開しておくということです。
当社では初期費用なども特に設定しておらず、サービス内容もデモを必要とするようなものでもありません。「企業のニーズに合うBizDev人材を月5万円からレンタルできる」というサービスであり、それ以上でもそれ以下でもありません。「シリョーズ」や「BizDevアカデミー」といった付帯サービスもすべて料金を公開しています。
もしかしたら最低金額の設定をしないほうが得られるリードの数や売上が大きくなったのかもしれませんが、先の導線から考えるとここも明示しておくほうがスムーズだろうと考えた結果です。
2期目に入り、登録者も日々増え続けるなかで、引き続き新規の営業活動は注力していかないとと思っています。水面下でいろんな活動を試してはいますが、主軸としてはこの考え方をベースにしながらやっていければと思っています。