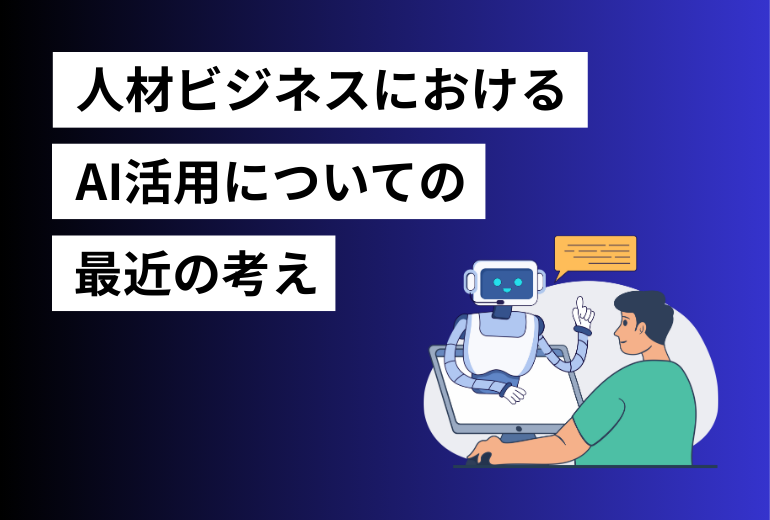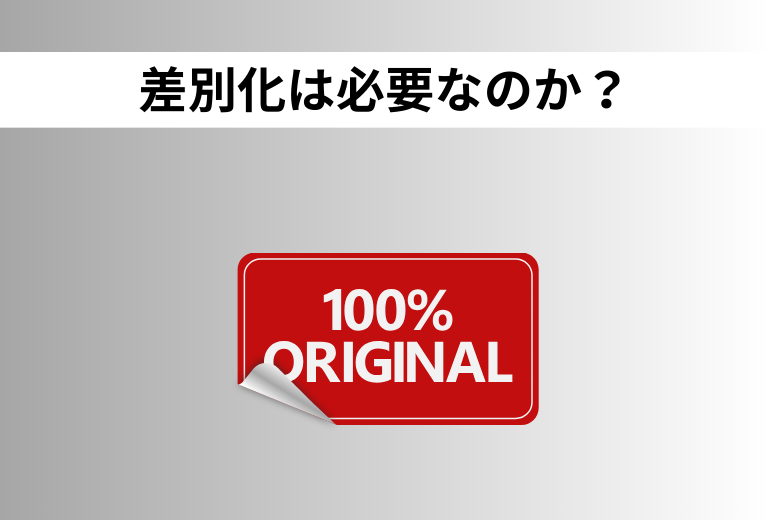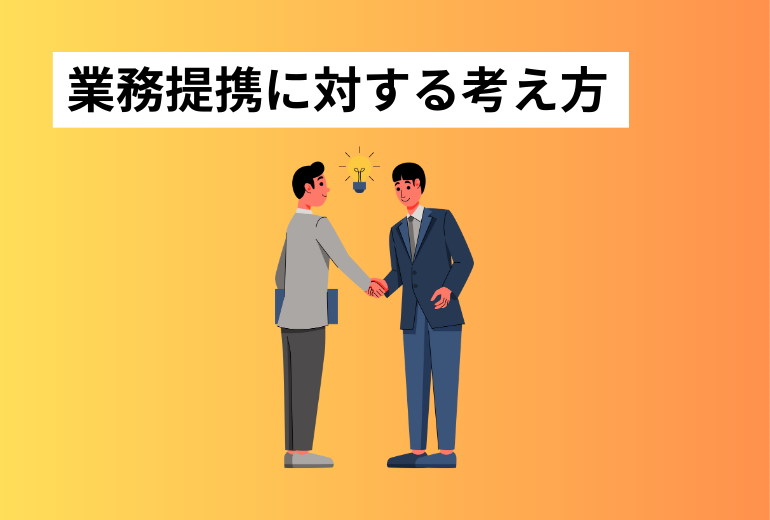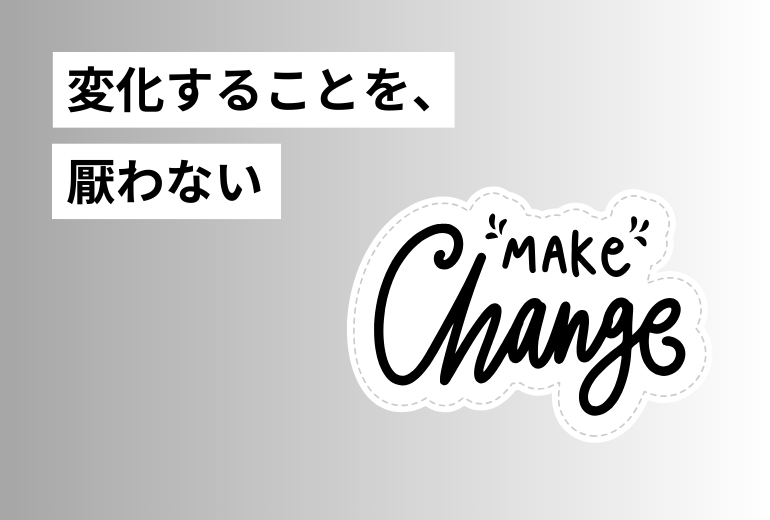自分の周りでも、日常的に生成AIを活用する人がかなり増えてきたように思います。
よく「どんな業務に使ってるの?」と聞かれますが、ひとことで言うのは意外と悩ましい。「月刊タレンタル」というオウンドメディアの運営だけで言っても、コンテンツのアイデア出しや文章生成、インタビューする人や企業の情報収集、インタビュー記事の添削など、非常に多くのシーンで使っています。営業活動や人材マッチング業務、あとは経理・法務などの専門業務においてもあらゆるシーンで活用しています。
ドラゴンボールで、セルと戦う前の悟空と悟飯が、精神と時の部屋に入るのですが、そこで悟空が、「まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気持ちをなくすために、寝ている時間以外はすべてスーパーサイヤ人でいよう」と悟飯に言うシーンがあります。個人的にはこのシーンがAI活用を考える上で一番しっくり来ていて、「寝ている時間以外はすべてAIとともに動く」のが理想的かなと思っています。
AIツールはなんでもいいと思いますが、自分の思考プロセスをすべてメモリとして蓄積しておくことで、その後のアウトプットの精度が格段に変わります。自分の場合は、毎晩寝る前に、今考えている新規事業や取り組みのアイデア、関心を持っているテーマなどを入れて壁打ちをして、そのやりとりを「ブログ記事風にして」と入れておきます。そうすると翌日以降も読みやすいコンテンツになるので、それを定期的に読み直して考えを深めたり、追加のリサーチを指示したり。経済価値の算出は難しいですが、これが一番効いている実感があります。
人材ビジネスにおけるAI活用ポイント
ちょっと話がそれてしまいました。
当社のような人材ビジネスを行う企業がAIを活用するときに、どんな使い方ができるか、整理してみましょう。
- リーガルチェック(契約書のリスク洗い出し)
- コンテンツ制作(オウンドメディア記事・SNS用文面の生成)
- 求人票の作成(候補者に魅力を感じてもらえる文章へのリライト)
- レジュメ添削(自然な日本語表現へのリライト、ブラッシュアップ)
- スカウト文面の作成(求人ごとにパーソナライズされた文面の作成)
一般的にはこの辺が活用シーンとして想像されるものだと思いますし、実際にAIで効率化している方も多くいらっしゃると思います。ただ、本丸はやはり人材ビジネスのコアであるマッチングアルゴリズムへの組み込みだと考えています。
従来は何らかのデータベースに人材データや求人情報データが蓄積され、職種や勤務地、年収などの条件での検索やキーワードマッチによる検索が基本でした。これだとどうしても表記ゆれや文章を理解した意味による検索ができず、マッチングが非常に属人的になってしまうという問題があり、大量のデータベースを有していても、結局「優秀なコンサルタントの頭の中にすべてがある」という状態から抜け出すことができません。
しかし、生成AIがここをクリアしてくる可能性が高くなっています。文脈や意味を理解し、少なくとも候補者抽出の段階では人の記憶を大きく超えることができるように思います。当社でも約200名のタレントデータベースから日々企業のニーズに合致する候補者を抽出するところでAIを活用していますが、私自身の記憶に頼るよりも余程手ごたえがあります。何万件というデータベースを有する会社であれば、そのインパクトはさらに大きいでしょう。
ここで多くの会社がぶつかる壁が、「大量の機密情報や個人情報をAIにインプットして大丈夫なのか?」という点です。確かに、データベースを保管するツールからChatGPTなどのツールにそれを入れてしまうのは、セキュリティ上リスクが高く、推奨できません。
短期的な解決策のひとつとしておすすめしたいのが、Notion、Google Workspace、Microsoft 365といった、AIがインターフェース側に実装されているツールそのものをデータベースとして活用するという方法です。今後は、MCP(Model Context Protocol)などを通じて、AIにどこまでの情報を見せるかを構造的に制御しながら、より安全かつ柔軟な連携を実現する流れも進んでいくでしょう。このような方法であれば、セキュアなクラウド環境でデータを外に出すことなくAIが使える。これだけで、かなり安心感が違います。ちなみに当社ではNotion DB × Notion AIという構造でデータベースを保有しています。
参考:AI業務活用の鍵を握るMCP(Model Context Protocol)とその実践的活用法
データそのものは従来のクラウド環境に保持し、抽出部分のインターフェースでAIを活用することで、既存の業務フローを大きく変えずに、AIのメリットを享受することができます。ユーザーの操作ログ、アクセス履歴などもきちんと取得することができます。
もちろんデータベースそのものを移管する必要があるため、決して簡単な話ではありません。ですが、今後の業務フローを考えるにあたって、データベースを保有する母艦とそこでのAI活用をどう設計するかが人材ビジネスの肝となることは間違いありません。当社としても様々な選択肢を検討しながら、最適な方法を模索していきたいと思っています。